|
|
2006�N4���O��
�@�C������������4���B���N������4����1�I��������B�����A��������B
�@�����͒��O�ɋN���āA�W�[���E�E���t���w�f�X���m�̓����̑��̕���x��ǂݏI���āA���Ƃ͂����Ɗ��z�������Ă����B�o�J�݂����B
�@permalink | 

�@�\�̃W�[���E�E���t�w�f�X���m�̓����̑��̕���x��ǂݏI�����B
�@�ǂݏI����̂ɉ��\�����������B�N�x���ň��݉���������̂ƁA���Z�ҏW�������̂����R�̈�Ȃ̂����i�l�̏ꍇ�����̕��ꐢ�E�ɓ��荞�ނ܂łɂ�����Ǝ��Ԃ��K�v�ŁA���Z�ҏW�͈�̕����ǂݏI����Ǝ��̘b�������ɑ����ēǂ߂Ȃ��̂ł���j�A�E���t������Ȃɂ�������Ƃ��Ɨ�������̂ɔ������炢�ǂ�ł悤�₭�C�Â�������Ƃ����̂���ԑ傫�ȗ��R��������Ȃ��B��ԋC�ɓ����Ă���̂́A�u���̓��̔��m�v�Ȃ̂����A���̍�i�ł����Ō�̐��y�[�W��ǂ�ŏ��߂Ă������������Ɗ��S�����̂������B�������Ǝv���Ă���́A���Ȃ萨�������Ă����ɓǂݏI�����̂����A��҂��Ƃ̓��e���������邽�߂ɁA�Ȃ��Ȃ����̍�i�ɓ���Ȃ��Ƃ������ۂ������Ȃ����B
�@�W�[���E�E���t���w�P���x���X��܂̎�x�Řb��ɂȂ��Ă���2�N���炢�o�̂��낤���B�C��������w�f�X���m�̓����̑��̕���x���V���ŏo�Ă����B�u�f�X���m�̓��v�Ƃ������t����C���[�W������̂��Ǐ��ӗ~��������A�x����Ȃ���ǂ�ł݂��킯���B�^�C�g������ʔ����Ƃ������A�l������Ă���Ƃ������A�ς���Ă���B�\���́u�f�X���m�̓����̑��̕���iThe Island of Doctor Death and Other Stories�j�v�̑��̎��^��́u�A�C�����h���m�̎��iThe Death of Dr. Island�j�v�u���̓��̔��m�iThe Doctor of Death Island�j�v�A����Ɓu�A�����J�̎���v�u��M�̊�ցv�ł���B�^�C�g�����A�i�O�����ɂȂ��Ă���Z�҂́A���ꂼ��P���ȕ���̑��҂ł͂Ȃ��B�u�A�C�����h���m�̎��iThe Death of Dr. Island�j�v�́A�u�f�X���m�̓����̑��̕���iThe Island of Doctor Death and Other Stories�j�v�̃^�C�g�������ł͂Ȃ����낢��Ȃ��̂𗠕Ԃ��ɂ����ʂ̕���Ȃ̂ł���B
�@�Ȃ�ł���Ȃ��Ƃ����悤�Ƃ������́A�u�܂������v�ɏ�����Ă���̂ŏȗ����邪�A���́u�܂������v�̂��܂��ɂ́A�u���̔��m�̎��iDeath of the Island Doctor�j�v�Ƃ���4�Ԗڂ̏��҂�������Ă��邩�狰�����B�u�܂������v�ɂ��܂��̒Z�҂������Ƃ����̂́A�����B��Y�̉���ɂ��A�u�o�ŎЂɂ��A�N���܂������͓ǂ܂Ȃ��������v����O������ǂ�ł���u�I�ꂽ�����h�v�ւ̓��ʂȑ��蕨�炵���B�����Ă��̂����₩�ȑ��蕨���Ȃ��Ȃ����炵�����҂������B
�@�ڎ��Ŏ��^��i�������āA�����̃A�i�O�����V���[�Y�̐��܂ꂽ�������Ɓu���̔��m�̎��v��ǂ�ŁA�W�[���E�E���t�͂Ȃ��Ȃ��ʔ��������Ǝv��������ǁA�܂����̎��_�ł͂���Ȃɂ������Ƃ͎v���ĂȂ������B�{�̏Љ�Ƃ��ẮA����ŏ\�����Ǝv���̂ŁA���Ƃ͍�i�̓��e�ɂ��ĐG���B����ȏ�̏Љ�͕s�v�����A�ނ�����e�ɂ��Č�荇����������Ȃ��B�����ł͌�荇���Ƃ͂����Ȃ��āA����I�Ɋ��z���������������ǁB
�u�f�X���m�̓����̑��̕���v
�@�f�X���m�̕����ǂ�ł��鏭�N�ƕ���̈��p���A���̊Ԃɂ����N�̌����ɕ��ꂪ������n�߂�Ƃ�������B��l�����̒��őދ��ȂƂ��A��z�̕���Ɉ������̂́A�������Ǐ���D�����N����������悭�킩��C�������B���N�̌����Ƌ�z�̍����������ꂪ�A�ق�Ƃ��ɒP�Ȃ��z�Ȃ̂��^��Ɏv�킹��o��������������A�s�v�c�Ȋ������o���Ă���B�f�ГI�ɂ����o�Ă��Ȃ��u�f�X���m�v�̕�����A�����ۂ�B��SF�f��I�Ȑ��E���Ȃ�Ƃ����͓I�����A�����SF�Ƃ������m�X�^���W�b�N�Șb���Ǝv���Ă����B�Ƃ��낪�Ō�̈�s�ł����Ȃ胁�^�t�B�N�V���������Ă��܂��B
�@�ł��܂����̍�i��ǂ��_�ł́A�E���t�̂������ɂ͋C�Â��ĂȂ������B
�u�A�C�����h���m�̎��v
�@�u�f�X���m�̓����̑��̕���v�̗��Ԃ��Ƃ����̂�����ǁA����ȒP���ȗ��Ԃ�����Ȃ��B�����܂������ʂ̕���ŁA����̔w�i���킩��܂łɂ����Ԃ�������B�ǂ��������̓��̕���ł��邩�̂悤�Ɏn�܂邪�A�u�f�X���m�̓����̑��̕���v�Ƃ͑ł��ĕς���āA����͖����A�ꏊ�͒n���ł���Ȃ��B�A�C�����h���m�́A�����̂��̂ł���A�g�̉����g���Ē���A�����߂̖������g���Ē���A���̖�����ʂ��Ē���B
�@���̓��ɂق��ɂ���̂́A�����ƃC�O�i�V�I�Ƃ����댯�����Ȓj�B�ނ�͂Ȃ����̓��ɂ���̂��A���̓��͈�̂Ȃ�Ȃ̂��A����炪�����Ă���ƂƂ��ɁA�ˑR�K���J�^�X�g���t�B�j�]�̂悤�ł��āA���͑�c�~�ł�����Ƃ��������B
�@�����A�C�����h���m�̐��́A�����A�C�O�i�V�I�A���N���Ȃ������ɂ����̂��A���N��<�߂���>�B�����Ȃ��Ƃ��킩�����͂��Ȃ̂ɁA���ǂǂ��������Ƃ������̂��킩��Ȃ��Ȃ��Ă܂��ǂݕԂ��Ă��܂��B�����[���B
�@�u�f�X���m�̓����̑��̕���v�̗��Ԃ��������͂��Ȃ̂ɁA������Ǝv���Ă܂��l����B
�u���̓��̔��m�v
�@�u���̓��v�Ƃ��������x�͌��t�ǂ���̓��ł͂Ȃ��B�I�g�Y�̎�Y�҂ł��锎�m�����ɐN����A���Âł���܂ŗⓀ�~������B�ڂ��o�܂����ނ́A�����̎��ÂŎ��ȂȂ��[�ɂȂ��Ă����B���ȂȂ��I�g�Y�̎�Y�҂��Z�ތY���������̓��ƗႦ����B
�@���̎���A�{�͓ǂނ��̂ł͂Ȃ��A�Θb������̂ƂȂ��Ă���B�y�[�W���J���Ɩ{������̂��B���̔����������̂��A��l���̎�Y�҂̔��m�ł���B���̔����ɂ܂��b�ȂǁA�Ō�̐��y�[�W���������B
�@�{�̒����甲���o���ʂ̖{�̒��ɓ����Ă��܂��A�L�����N�^�����B���̍�����ɁA�I�g�Y���ɂ��悤�Ƃ�����������锎�m�B�ʂ����Ă��̖{�̒�����L�����N�^�������o���͎̂��̂Ȃ̂��A���m�̌̈ӂ̖d���Ȃ̂��B�o����҂��Ă����̂̏����\���Ă���͎̂��i�ɂ����ďe���\���Ă���̂��A�P�Ȃ�J�����Ȃ̂��B
�@���̐��y�[�W�̌�ɑ��������͉��ʂ���l������B���O�܂ŁA�l�X�Ȗʔ����A�C�f�B�A�Ɋ��S���Ȃ���ǂ�ł͂����̂����A���̍Ō�̐��y�[�W�Ŗ{���Ɋ��S�����B�����Ƃ��Ċ������Ă���Ǝv����̂����A���ꂾ�����肾������̃A�C�f�B�A������߂��āA����̑��������낢��l������܂I����Ă��܂��Ȃ�āA���������Ȃ��Ǝv�����B����̃G�s�\�[�h���܂ޕʂ̒��ҏ������������ׂ����A�ǂ݂����Ǝv�����̂��B�ł��A���̏������̂��K��g���{���Ƃ��A���������Ƃ��v��Ȃ��B
�@��������̌�������邱�Ƃ����Ăł���̂����A�����͂����ɂ����Ă����ŏI����Ă���̂ł����āA���Ԃ�W�[���E�E���t�ɂƂ��Ă͂���ȊO�̌����͂��肦�Ȃ���Ȃ����Ǝv����̂��B����A�{���͂���ɂ����Ə����������������邯��ǁA���̒��̈��I������������Ȃ����B
�@���̌�����ǂ�ō��܂œǂ���������Ɠǂ݂���Ă��Ȃ���Ȃ����Ǝv�����B�Ǐ��͕��͂̓lj�͂ƂƂ��ɑz���͂�v�����邪�A�W�[���E�E���t�̏����͂��̑z���͂��ő���ɔ��������邱�Ƃ�v�����Ă���B�v�����Ă�̂ł͂Ȃ��āA�ǎ҂ɑI���̗]�n��^���Ă���Ƃ��������������̂�������Ȃ��B����Ȃ킯�ŁA�����͓ǂݏI������̂ɓǏ��͏I���Ȃ��̂ł���B
�@�Ƃ������ƂŁA�悤�₭�W�[���E�E���t�̂�����������������B����Ȃɓǂ݂ł̂���{�i�y�[�W���ł͂Ȃ��j���āA�v���Ԃ�ɓǂC�������B
�u�A�����J�̎���v
�@�W�[���E�E���t�̏����͖���������Ⴄ���A�d�|���Ƃ�������@�Ƃ������A�����S�̂̍\�����Â��Ă��邱�Ƃ͗��������B�u�A�����J�̎���v�͍��x�͓��L�`���ł��邪�A���ꂪ�����̓��L�ł���킯���Ȃ��B
�@���炷���������Ă��܂��ƈӊO�ƒP���Șb�ł���B��ʂ̎莆��������A�s���s���ɂȂ����q���̓��L�𑗂�R������Ă���B�����̖{�҂͂��̎q���i�_���̓��L�ł���B���L�ɂ͋ߖ����A�h���b�O�Ȃǂ̉e���Ȃ̂������A�����J�A�����c��A�����J�l�����͊�`�������蕂�Q�҂ƂȂ��Ă�����A���������Ă��܂����l�X������Ƃ����ߎS�ȃA�����J�ʼn߂��������Ԃ̏o������������Ă���B
�@�������ꂾ������Ȃ��B�����������L�̏�����i�_�������ׂĐ^���������Ă���̂��͂킩��Ȃ��B�h���b�O���َq�ɐ��ݍ��܂����V�A�����[���b�g���ɐH�ׂĂ����ނ͌��o�����Ă��邩������Ȃ��B��҂̖����B��Y�̉���ɂ��A���L�̓^�C�g���̎���ɂ͈�鑫��Ȃ��Ƃ����B���̈��̓h���b�O�̌��z�Ŕ��ł��邩������Ȃ��Ƃ����̂����A������肩�ł͂Ȃ��B������Ă�����L�̂����ꂩ�����o�Ȃ̂�������Ȃ����A���ׂĐ��C�ł���ΒN�����E�э���������Ȃ��`�Ղ������Ƃ������ƂɂȂ�A�N�����X�p�C���Ă���Ƃ������Ƃ������ɂȂ�B
�@�����āA�Ō�ɂ̓i�_���̕�e�����L��ǂݏI�������ƁA���L�̕M�Ղ����q�̂��̂��₢������B�܂�A���L���̂��̂��{�����ǂ������킩��Ȃ��킯���B
�@���I�`���čŒ�̃I�`�̈�Ƃ��Ă悭�������邪�A���I�`���_���Ȃ̂͂���܂ł̕���S�̂��S�ے肳��Ă��܂��悤�ȃp�^�[���̂Ƃ����Ǝv���B����������Ȃ��A�ł������łȂ���������Ȃ��Ƃ����]�n���c����Ă��Ȃ���A���I�`�Ƃ��Đ������Ă��Ȃ��B���́u�A�����J�̎���v�̍Ō�́A�ǂ��܂ŐM���Ă���������Ȃ����L�ɁA�Ō�ɑʖډ����ł���ɓ��L���̂ɂ��^��������Ƃ����A�悭�ł������I�`�Ɏ����I������Ǝv���B
�@�u�f�X���m�̓����̑��̕���v���l���Ă݂���̃p�^�[���̕ό`��������Ȃ��B
�u��M�̊�ցv
�@���ꂪ��Ԏ育�킢��i���낤���B�u�f�X���m�̓����̑��̕���v�ŏ��N�̌����Ƌ�z�������荇���悤�ɁA���̕���̎�l�����g���E�e�B�u�̎�ς��ǂ��܂Ō����łǂ��܂ŋ�z�Ȃ̂��킩��Ȃ��B��z�Ƃ������A�ނ���u�A�����J�̎���v�̃i�_���̌��o�̂悤�ɂ��̂�������Ȃ��B���������g���E�e�B�u�͖ӖڂƂ������B�ނ��m�o���Ă�����̂��ǂ��܂Ő������̂��킩��Ȃ�����A�����ȑz�������Ă��܂��A�����������ꂪ����ɍ������Ă����B�������A���ꂱ���W�[���E�E���t�̑_���Ȃ낤���ǁB
�@�������������ƌ��z�̍����ŕЕt�������ɂȂ����㔼�A�ˑR���e�̓o��Ƃ��̐����Ŗ��m�ɂȂ�B�u�A�C�����h���m�̎��v�œ��̔閧�����炩�ɂȂ����Ƃ��ɂ�����������������B���܂Ō����ɂ͂��肦�Ȃ��Ǝv�������̂��ˑR�����I�Ȃ��̂ւƂЂ����肩����B������đS���A�Z���X�E�I�u�E�����_�[�Ȃ̂����A���炩�ɂȂ������Ǝv�����Ƃ���ŏI��炸�ɁA�܂������ƌ����ƌ��z�����荬�������`�ŕ��ꂪ�I���B
�@�Ō�Ƀ��g���E�e�B�u�ƃj�b�e�B�ƃh���V�[�����H�̏������Ă��������͂ƂĂ������B�h���V�[���ꏏ�Ȃ̂͌��z�Ȃ̂�������Ȃ����A���g���E�e�B�u�ɂƂ��Ă̓h���V�[�������Ȃ̂�������Ȃ��Ǝv���ƁA���ǂǂ��܂ł������łǂ����炪���z�Ȃ̂��킩��Ȃ��Ȃ�B������������S�������Ȃ̂�������Ȃ��킯�ŁB
[ �w�f�X���m�̓����̑��̕���x�@�W�[���E�E���t�@�������s�� ]
�@permalink | 
�@������w�f�X���m�̓����̑��̕���x�̊��z�������Ă������ɂȂ��Ă��܂��A�ǂ��ɂ��o�������d�����B����Ȃ킯�ŗ[������A�w�{�[���E�R���N�^�[�x�i�W�F�t���[�E�f�B�[���@�[�j��ǂݎn�߂�B
�@�f���[���E���V���g���ƃA���W�F���[�i�E�W�����[�ʼnf�扻���ꂽ����ł���B�e���r�ł����x����������Ă��邯�ǁA�]���̂�������𖢓ǂȂ��ߔ����Ă��āA�܂��ς����Ƃ��Ȃ��B
�@����́w�{�[���E�R���N�^�[�x�͗\�z�ʂ�ʔ����̂����A���������ƂɁw�f�X���m�̓����̑��̕���x�̌�ɓǂނƂ܂�Ȃ��������̂������B���܂�Ƀ��[�_�u���Ȋ��������āA�����ƂЂ˂�͂Ȃ��̂��Ƃ��v���Ă��܂��̂��B
�@�ł����̈Ⴂ�͖ʔ����A�܂�Ȃ��̂ł͂Ȃ��āA�S���Ⴄ�ʔ����ɓ�����ւ���Ă��Ȃ��낤�Ǝv���Ă���B
�@���܂������ł��Ȃ��̂ŗႦ��ƁA�s�J�\�̒��ۉ��������ɁA���C�G�X�̐����ȉ�������悤�Ȋ����A�Ȃ�Ă����̂��l���Ă݂��B�s�J�\�̊G�͉��߂Ȃǂ��܂߂Ă��낢��l���Ȃ��ƌ����Ȃ����낤���A���C�G�X�̉�͎ʐ^�݂����ȉ�ɂ������ߑ������Ƃ������B�ƁA�l���Ă݂��̂����A���C�G�X�̉�̓s�J�\����������Ɍ��Ă������đދ��Ƃ͊����Ȃ����낤�Ǝv���Ă��܂��A���܂���ɂȂ�Ȃ������̂����B
�@�ł��w�{�[���E�R���N�^�[�x���ʔ����͎̂����ŁA�Ƃ肠������C��3����2��ǂB�������A�Q��9���߂��ɋN����B���H�Ȃǂ����Ȃ��瑱����ǂ�œǗ��B
�@�[������J���~��B�Ԍ������Ȃ������ɍ����U���Ă���B
�@��A�A���e�i���\������Ȃ����ׂ�B�������ꂱ�ꉽ�����������Ă���s��Ȃ̂ŁA�������������Ȃ����Ⴂ���Ȃ��Ȃ��Ǝv���ďd�������グ���̂����A�Ȃ�̂��Ƃ͂Ȃ�30���������炸�����B����Ȃ��ƂȂ瑁�����悩�����B
�@permalink | 

�@�����܂ł��Ȃ��A�W�F�t���[�E�f�B�[���@�[�̃����J�[���E���C���E�V���[�Y�̑���ł���B�C�ɂȂ��Ă��Ȃ��獡�܂œǂ�łȂ��Ă悤�₭�ǂ���B
�@����Ȃ��ɖʔ����B���܂��܁w�f�X���m�̓����̑��̕���x�̌�ɓǂ̂ŁA�ǂݎn�߂Ă��炭�͂��܂�Ƀ��[�_�u���ȋC���������A��C�ɓǂ܂���͂������Ă���B���܂�ɗL���ȍ�i�ŁA����6�N�ȏ�O�ɖ|��Ă�����̂Ȃ̂ł��܂���Ƃ����C�����邪�A���������Ă��܂��Ɩl�ɏ����銴�z�Ȃ�ĂȂ��Ȃ��Ă��܂��B��ɂ���āA���e�ɐG���̂ŏЉ�����҂��Ă���l�͂����ӂ��B�v����ɁA����Ȃ��ɖʔ����̂œǂ����������Ă���̂Ȃ�A���ǂނׂ����Ă��Ƃł���B
�@�����Ȃ�Ɛl�̂��Ƃ������Ă��܂��ƁA�ߋ��̔ƍ߂�����{�ɔƍ߂�Ƃ��킯�����A���̂���{�ƂȂ�ߋ��̔ƍߎ҂��Ȃ�ƂȂ��u��W���b�N�v���ۂ������āA���\�C�ɓ����Ă���B���̔ƍߎ҂�ǂ��l����Ⴢ̃����J�[���E���C���̓��]�v���C���ʔ����B�ƍߎ҂����̎����̗\�������āA���C�������̓�����������𖢑R�ɖh�����Ƃ���B
�@�悭�����閼�T��قǁA��Q�҂����E���ɂ��Ă����Ȃ����Ƃ����b�����邪�A���C���̏ꍇ���Ȃ�̊m���ŋ~���Ă���̂��f���炵���B����I�ȗ�E�l�����Ƃ�������ł���Ȃ���A�Ɛl�ΒT��̑Ό��Ƃ����̂Ȃ���̐}����g�ݗ��ĂĂ���̂��A�ʔ����̗��R����Ȃ����Ǝv���B�R�[���E�F���̍�i�ȂǁA�ʔ����Ǝv���Ȃ�����A��Q�҂����X�Ɩ��c�ȎE����������Ă����Ƃ���J�T�ɂȂ��Ă���B
�@�����ЂƂ����Ƃ���́A�ÓT�I�Ȗ{�i�~�X�e���̍\�}�ɂȂ��Ă���̂ɁA���̂��Ƃ�ǎ҂ɋC�Â����Ȃ��_�ł���B��́A�~�X�e���̔Ɛl�͂悭�ł��Ă���~�X�e���قǁA�i����̒��ł���A�ǎ҂̓��̒��ł���j�ŏ��ɗe�^�҂���͂������B�w�{�[���E�R���N�^�[�x�ł��A�~�X�e���̌����ʂ�Ɛl�͍ŏ�����o�ꂵ�Ă���̂����A���C���̊����`������I�ȃ~�X�e�����Ǝv�킹�āA����ɑ��������ʎ����̘A���ŁA������C�Â����Ȃ��B
�@�w�{�[���E�R���N�^�[�x�Ƃ����^�C�g���Ȃ̂ɁA�Ɛl���{�[���E�R���N�^�[�ƕ\�L�����̂͂��Ȃ�x���B���C�������̕W�{�������Ă����ʂŁA���������āw�{�[���E�R���N�^�[�x���ĔƐl�̂��Ƃł͂Ȃ��āA���C���̂��Ƃ������̂��Ǝv�������ƁA�{�[���E�R���N�^�[�Ƃ����\�L�₻�̗R���������B
�@���C�����u�{�[���E�R���N�^�[�v�Ȃ̂��Ǝv�����̂����Ȃ����ԈႢ�łȂ������̂��ȂƎv���āA�ӂƋC�Â����̂́A�܂肱�̎��_�ł��ǎ҂ւ̃q���g������Ă������Ă������Ƃ��B
�@�Ȋw�{���ׂ̍����`�ʂ�ςݏd�˂Ă����ȂǁA����߂Č���I�ȃ~�X�e���̂悤�ł��āA���͂��Ȃ�{�i���������̍��g�݂���낤�Ƃ��Ă����i�Ȃ̂��B
�@���E��]�̋������C�����A�����ł����ԐS���h�炮���̂́A���ǂ͕ς��Ȃ��Ƃ����̂������B�������C�������ς���Ă��ꂽ���������̂����A�l���Č��������4���Ԃ̕���Ȃ̂ł���B�l�̋C�����Ȃ�Ă���ȊȒP�ɕς����̂���Ȃ��B����ɂ��Ă��A���̕������{��������4�������Ă����̂��l���Ă݂���������B
[ �w�{�[���E�R���N�^�[�x�@�W�F�t���[�E�f�B�[���@�[�@���t���� ]
�@permalink | 
�@�w�{�[���E�R���N�^�[�x�ɑ����A�����J�[���E���C�������w�R�t�B���E�_���T�[�x�i�W�F�t���[�E�f�B�[���@�[�j��ǂݎn�߂�B
�@�ł�����������݂ɍs���ēǏ��͐i�܂Ȃ��B
�@permalink | 
�@����͈��݂����āA���̊Ԃɂ��Q�Ă����B6���ɋN���Ē����C���������n�܂�B
�@�����āA�������˔��I�Ɉ��݉�B���������w�R�t�B���E�_���T�[�x�i�W�F�t���[�E�f�B�[���@�[�j�́A�����20�y�[�W��������̒��x�Ǐ�ԁB
�@�������܂����݂����B
�@permalink | 
�@�T�̏��߂�����݂����Ȃ̂ŁA�����͂܂������A��B�ƂŖA�������ށB�܂��A���Lj���ł��邯�ǁA����Ȃɂ���������ނ킯����Ȃ��̂Œ��x�݁H
�@��A���낻��A�h���͐V�����h���}�̘b�肪�o�n�߂Ă��鍡���ɂȂ��āA�u����s�v�̍ŏI����ς�B�ŏI��܂ł͏����ɊςĂ����̂����A�O�ɂ��������悤���u�A���t�F�A�v�ɂ��܂�ɂ͂܂肷���āA�ŏI���ςĂȂ������̂��B�悤����ƁA�u�A���t�F�A�v�M�����������āA�u����s�v���ςȂ�����Ǝv��������B
�@�������A�u����s�v���܂�Ȃ������킯����Ȃ��āA���ꂪ�܂��ʔ��������B�ŏI����ϏI���āA�܂��������ɂȂ��Ă��܂������Ȃ��炢�����������Ƃ�����̂����A�����͎��Ԃ��Ȃ��̂ł܂����x�����B
�@�u�A���t�F�A�v�̖ʔ����Ƃ͂�����ƈ���Ă��IJ�A�����������Ƃ́A�h���}�u����s�v�ɂ��ẮA���쏬���w����s�x���ǂ��r�F�������Ƃ������Ƃɐs����B
�@�u����s�v��1�b���ς��Ƃ��Ƀ~�X�e���̃h���}���Ƃ��Ă͍Œ�Ȃ��ƂɁA����̌������ŏ��Ɍ����Ă��܂��B����́A�Ɛl����𑤂ɂ���̂Ō����ȃt�[�_�j�b�g�ł͂Ȃ��̂ŔƐl���N���Ƃ������Ƃ͂���Ȃɏd�v�ł͂Ȃ����ŏ��̃V�[��������ł����̂��Ǝv�����A�t�[�_�j�b�g�łȂ�����z���C�_�j�b�g�ł���̂ɓ��@�����炩�ɂ��Ă��܂��B����͍�������Ǝv�������̂����A�~�X�e���������h���}�ɂ��Ă��܂��ȏセ����d���̂Ȃ����Ƃ��낤�B
�@�ł����ꂪ�����ǂ�ł���l�ɂ��A�Ƃ����������ǂ�ł���l�ɂ��������͂�����悤�ȃX�g�[���[�ɂȂ��Ă��āA����Ɋ��S�����̂��B
�@�Ƃ������n�߂��2�A3���Ԃ����肻���Ȃ̂ł���ς��ŏ����B�ł��A�����n�߂�ƁA�܂��^����Ď��������肵�āA2�A3���Ԃǂ��납����ׂ���Ȃ����Ƃ����C������B�Ƃ�����Ȃ��Ƃ��Ă���ɂ͂���̂��B�Ȃ�ƂȂ��A���̑������������Ԃ��Ƃ��̂��S�z�ɂȂ��Ă����B
�@�����A���Ă������ǁA�d�Ԃł͖��������肵�āA���ǂ�ł����w�R�t�B���E�_���T�[�x�i�W�F�t���[�E�f�B�[���@�[�j�́A������Ɛi�����B
�@permalink | 
�@������[���܂ŊO�o�B
�@��͍��T�O��ڂ̈��݁B���ꂼ��ʂ̈��݉���ǁA3��Ƃ������l����l�ꏏ�ŁA�v����Ɉ��ތ���������Ă邾���݂����ł���B�����Ȃ��̐l�Ɠ�l�����肾���B
�@�Ǐ��͋O���ɏ��n�߂邪�A����ł�����Ȃ̂ł���ς�Ǐ��͐i�܂Ȃ��B
�@permalink | 
�@�w�R�t�B���E�_���T�[�x�i�W�F�t���[�E�f�B�[���@�[�j�̓Ǐ����ʔ����Ȃ��Ă����̂ŁA��͂܂������A���ēǏ��B�c��O���̈�͖����̊y���݂Ɏc���ĐQ��B
�@permalink | 
�@�w�R�t�B���E�_���T�[�x�i�W�F�t���[�E�f�B�[���@�[�j�Ǘ��B�����J�[���E���C���E�V���[�Y�͉\�ǂ���ɖʔ����̂ŁA�����đ�O���w�G���v�e�B�[�E�`�F�A�x�i�W�F�t���[�E�f�B�[���@�[�j�ɍs�������Ƃ��v�����̂���������ƒE���A�w�g�����F���[�x�i�W�����E�g�E�F�����E�z�[�N�X�j��ǂݎn�߂�B
�@�w�g�����F���[�x�́A�{���Ō��������ہA�u�w�_�E���B���`�E�R�[�h�x�i�_���E�u���E���j�̃`�[�����͂ȂŐV�����v����`����Ă��āA�u�H�v�Ǝv�����̂����������ŋ������������B�f��Ȃ�킩��̂����ǁA�Ȃ�ŏ����Łu�`�[���v�Ȃ̂��Ǝv�����̂��B�����̖�҂��Ƃ���������ƁA�w�_�E���B���`�E�R�[�h�x�̑�q�b�g�ŕҏW�҃W�F�C�\���E�J�E�t�}���̌��ɂ͑����̍�Ƃ��甄�荞�݂��E�������������B����Ȓ�����A�J�E�t�}�����ڂ������̂��S���̖����̍�Ƃ̐V�V���[�Y�ŁA���̑���ڂ��w�g�����F���[�x�Ȃ̂��������B
�@����Ȃ�A�u�w�_�E���B���`�E�R�[�h�x�̕ҏW�҂����o�����V���ȍ˔\�v�Ƃ��Ȃ�Ƃ������悳�����Ȃ����A�J�E�t�}���̃v�����[�V�����͒P�ɏ�����Ƃ�����������Ȃ��悤�ŁA���Ƀ��j�o�[�T�����f�扻�����l�������Ƃ��A�ē̓X�r���o�[�O���ȂǂƂ����āA�����Web�T�C�g������Ă̐�`�ƌ��\�h��Ȕ���o���������Ă���B�����Ȃ�ƁA���������ł͏I���Ȃ��āA�f��A�Q�[���ȂǗl�X�ȕ���ɓW�J���鑍���G���^�e�B�����g�ȂˁB
�@�����̍�҂́A���������v�����[�V�������C�ɓ���Ȃ��炵���āA�\�ɏo�Ă��Ă��Ȃ��B�u�n��̃p���[���E�����v�Ƃ������R�ŁA�v���t�B�[���̌��J���C���^�r���[�Ȃǂ̐�`��������؋��ۂ��Ă���Ƃ��B�ʔ����b���B
�@����Ȃ킯�ŁA�w�g�����F���[�x��ǂݎn�߂��B
�@permalink | 
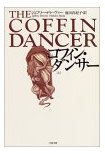 �@�����J�[���E���C���E�V���[�Y����ł���B�O�삩�炵�炭���Ԃ��o���Ă���A����قǎ��E�ɌŎ����Ă������C���͎��E���l���Ă��Ȃ��B�A�����A�E�T�b�N�X���悫���_�Ƃ��Ċӎ���i�߂Ă��邪�A�����E�Z���b�g�[���V���Ȏ�������������ł���B���̎����̒����𒆒f���Ă��A���C�������ւ�肽���Ǝv���͂����Ƃ����̂́A�E�����R�t�B���E�_���T�[�̍s����ǂ����Ƃ������B
�@�����J�[���E���C���E�V���[�Y����ł���B�O�삩�炵�炭���Ԃ��o���Ă���A����قǎ��E�ɌŎ����Ă������C���͎��E���l���Ă��Ȃ��B�A�����A�E�T�b�N�X���悫���_�Ƃ��Ċӎ���i�߂Ă��邪�A�����E�Z���b�g�[���V���Ȏ�������������ł���B���̎����̒����𒆒f���Ă��A���C�������ւ�肽���Ǝv���͂����Ƃ����̂́A�E�����R�t�B���E�_���T�[�̍s����ǂ����Ƃ������B
�@���C�����_���T�[�ɌŎ����闝�R�́A���C���̕������ӎ������悤�Ƃ����Ƃ��ɁA�d�|����ꂽ���e�ɂ���ĎE���ꂽ�Ƃ������Ƃ�����B�ړI�͏؋��B�łł���B���ꂭ�炢�����ɏ؋����c���Ȃ��_���T�[�����A���C���͑O�쓯�l���؋����珙�X�Ƀ_���T�[��ǂ��l�߂Ă����B
�@���ʂɍl����ƁA����̓��C���̕������Ȃ�L���ȗ���ɂ���悤�Ɏv����B�_���T�[�͎O�l�̐l���̎E���𐿂������Ă��āA����̖`����l�ڂ���s�@�̔��j�ɂ���ĎE�����B�c���l�͌x�@�ɕی삳���̂ŁA�_���T�[�͕s���ȏɒu����Ă邢��B�������A�W�I�ƂȂ����l���͖��d�ɂ��x�@�̕ی���������̉�Ђ���邱�ƂɌŎ����āA����_���T�[�̎��ւƏo�čs���^�������Ă��܂��B�����Ȃ�Ȃ���A�b�ɂȂ�Ȃ��킯�����B
�@���C���̊�ł��A�A�����A�E�T�b�N�X�̊�ł�������Ȃ���A���̕W�I�ƂȂ鏗�����p�[�V�[�E���C�`�F���E�N���C���܂���łł��ꂪ����̎��ɂȂ��Ă���B���C�������̌x�����������A�����̔�s�@��Ђ���邽�߂Ɍ_��𗚍s���Ĕ�s�@�������Ƃ���B���̃p�[�V�[�ɑΗ���ԓx���A�A�����A�E�T�b�N�X�Ɏ��i���N��������B�w�R�t�B���E�_���T�[�x�́A���C���_���T�[�̑Ό��̕���ł����邪�A���C���ƃA�����A�E�T�b�N�X�̗����̑��i�K�̘b�ł�����B����炪�A�ނ�̐��i�ȂǂƂ����ݍ����Ă���̂ŁA�[���ł���B
�@����̓��C�����ƎE�����������݂ɕ`����A�T�X�y���X���̂Ƃ��ēW�J����̂����A�O�삪�T�X�y���X���̂��Ǝv���Ă�������͂�������Ƃ������������ɂ��Ȃ��Ă����悤�ɁA��������������d�|���������Ďv�킸�X�錋�����҂��Ă����B�^�����킩���Ă݂�ƁA�ł�����͂Ȃ���Ȃ����Ǝv���悤�ȂƂ������������̂����A���ꂾ���y���܂��Ă����Ƃ܂��ׂ����Ƃ���͂�����Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B�k���ȕ`�ʂ����͂Ȃ̂ɁA�����������������t�H���[�����Ă��܂����炢�ɂ́A�悭�l����ꂽ�W�J�ł���B
[ �w�R�t�B���E�_���T�[�x�@�W�F�t���[�E�f�B�[���@�[�@���t���� ]
�@permalink | 
�@�ߑO���͎G�p�����Ȃ��ĉ߂����B�ߌ��ɂ̓P�[�u���e���r�̒����Ƃ���������������B�n��g�f�W�^�������̎�M��Ԃ𑪒肵�Ă����Ƃ��B�ߌ�́A���̒����������邩�킩��Ȃ��̂ŁA�[���܂ŏo�������Ȃ��Ǝv���Ă����̂����A�ӊO�ɑ����Ƃ��������ԑO�ɂ��āA������Ƒ������ǂ����ł����Ƃ����̂ő劽�}�Œ��ׂĂ��炤�B
�@���A���{����������ƌ��ĉ��B�w�R�[�f�b�N�X�x�i���� �O���X�}���@�\�j�[�E�}�K�W���Y�j�Ƃ����{���ڂɗ��܂�B�C�M���X�Ńx�X�g�Z���[�ɂȂ��Ă���A���̖{���߂���b�炵���B���Ɂw�K�N�̖��O�x��w���i�x�̉��ɒu���ׂ��{�Ƃ������̂������āA�ʔ��������Ǝv�����̂����ǁA�]���͂ǂ��Ȃ낤�B�w�_�E���B���`�E�R�[�h�x�����A�n���ڂȊ������H�w��������̂����B
�@�Ǐ��͍���ǂݎn�߂��w�g�����F���[�x�i�W�����E�g�E�F�����E�z�[�N�X�@�\�j�[�E�}�K�W���Y�j�����X�ǂށB����̓��L�ɏ������悤�ɖ蕨����ŏЉ��Ă��邯�ǁA�Ȃ�ƂȂ����ʂ�SF�`�����̂Ƃ��������B�����Ƃ��܂�4����1���炢�����ǂ�ł��Ȃ����ǁB
�@permalink | 
 �@�ϑz�蒟�ɁATV�A�j���w���g���x�����J�n���ڂ��Ă�̂����ǁA����͍��ƂĂ��C�ɂȂ��Ă���A�j���Ȃ̂ł���B
�@�ϑz�蒟�ɁATV�A�j���w���g���x�����J�n���ڂ��Ă�̂����ǁA����͍��ƂĂ��C�ɂȂ��Ă���A�j���Ȃ̂ł���B
�@����͐A�ŗ�����w���g���x�B�m���Ă�l�ɂ͐����s�v�Ȃ̂����ǁi���ē�����O���j�A�w�i������ł����Ƃ������炢�`�����܂�Ă��閟��ŁA�G���͑S�R�Ⴄ����ǁA��F���m�A�������Y�ƕ��ԕ`�����n��Ƃł���B�������A�b���}�j�A�b�N�ŕs�v�c�ōD���Ȃ̂����ǁA������Ă����ȈӖ���TV�A�j�������s�\�Ȋ����Ȃ��ǁAOVA�ł͂Ȃ���TV�A�j���ł���Ă��܂��Ƃ����B
�@�T�C�g������ƁA�w�i�͂���Ȃ�ɕ`�����܂�Ă������ŁA���̊G���A�j���œ����Ƃ������Ǝ��̂�����Ɗ����Ȃ̂ŁA���̂������C�ɂȂ��Ă���B�^��\����ꂽ���ǁA�ǂ�Ȃ��̂ɂȂ�̂�������ƐS�z�B
�@�����������Ɗ�Ȃ����̂Ȃ̂ŁA�������[����������ǁA�e���r�����ɂ����ԕς���Ă��������ȁB���ꂪ�������ɓ]�Ԃ̂��������ɓ]�Ԃ̂��B
�@permalink | 
�@�N�x�ւ�̃h�^�o�^�͈�U���������B������������Ƒ����A��B
�@�w�g�����F���[�x�i�W�����E�g�E�F�����E�z�[�N�X�@�\�j�[�E�}�K�W���Y�j�͔������炢�܂œǂݐi�ށB�����Ă܂�Ȃ��͂Ȃ����ǁA����ς蕁�ʂ�SF�`�����̂Ƃ���������������Ȃ��BSF�Ƃ����ɂ̓Z���X�E�I���E�����_�[������Ȃ��B�P�ɐݒ肪SF�I�Ȗ`�����݂̂����Ȃ̂��B����̔w�i�̐��E���A�܂����ׂĂ͖��炩�ɂȂ��Ă��Ȃ��āA�^�C�g���́u�g�����F���[�v�͕ʂ̐��E�Ɉړ��ł���l�����������̂������ꂪ��̂ǂ��������ƂȂ̂��܂��o�Ă��Ă��Ȃ����A���ꂩ��ʔ����Ȃ�̂�������Ȃ����B�Ƃ肠�����A�����������҂����Ȃ���ǂ�ł������B
�@permalink | 
�@���w�r��27�K�Ŏd�������Ă���B�ӂƁA�O���݂�ƃ~���N�F�̕��i�B�����߂��̃r�����ڂ���ƌ�����ق��́A���������Z�����ɕ�܂�Ă���B������Ȃ��āA���J�������̂�������Ȃ����ǁB�O�������u�Ԃ͋h��������B
�@��A�w�i���j�A������x���ς�B�w�i���j�A����x�͐�Ɍ����ǂ�ł��������Ǝv�����̂����A���Ԃ����傤�ǂ悩�����̂ŁB�f����āA�ς悤�Ǝv�����Ƃ��ɊςȂ��ƌ������̂ŁA�������Ƃɂ����B
�@�������A�ŋ߁A�ς�f��̑I�𗝗R���قƂ�ǁu���Ԃ����傤�ǂ����v�ł���B���̂��������ؕԂ����ȁB
�@�Ǐ����w�g�����F���[�x�i�W�����E�g�E�F�����E�z�[�N�X�@�\�j�[�E�}�K�W���Y�j�ŁA���ɕ��ׂ��i�W�͂Ȃ��B���ׂ��i�W���Ă̂́A�u���߂�Ȃ����A�����Ԉ���Ă܂����B���̘b��������[!�v�Ƃ����������Ȃ�悤�ȗ\�z�O�̓W�J�Ȃ̂����A5����3���炢�ǂƂ���ł͈�ۂ��ς�炸�B
�@permalink | 
�@����́w�i���j�A������x�͓ǂ����Ǝv���Ă��ēǂ�łȂ���i�ŁA���ljf����ς�O�ɓǂނ��Ƃ��ł��Ȃ������B�Ȃ̂ŁA���삪�ǂ��f�扻����Ă��邩�ɂ��Ă͂킩��Ȃ��B
�@�f�扻���ꂽ�炻��͂܂�����Ƃ͕ʂ̍�i���Ǝv�����A�ʂ̍�i�ɂ܂ŏ�����Ă��Ȃ���A����͊ς鉿�l�̂Ȃ���i���Ǝv���B������A���삪�ǂ��f�扻����Ă���̂��͂���Ӗ��ǂ��ł������̂����A�w�i���j�A����x���炢�̍�i�ɂȂ�ƁA�ǂ��ł������Ƃ͌����Ă��Ȃ���ˁB�����ǂ�ł��Ȃ��l�Ԃ������̂��ςȘb�����B�ł��A����͂ǂ�ȍ�i�ɂ����ʂ��Ă��邱�ƂŁA���̕�����������Ɖf���ɂȂ�Ȃ��̂Ȃ�A���̕������`���Ȃ��̂Ȃ�A�f��ɂȂ��ė~�����Ȃ��A���Ă����̂͂ǂ�ȍ�i�ł����ʂ̘b���B
�@�����m�炸�ɂ����Ȃ�A�f��Ƃ��Ă͖ʔ��������B�f��̗͂Ƃ������́A����̗͂Ȃ̂��ȂƂ����C�͂��邪�B
�@�w���[�h�E�I�u�E�U�E�����O�x�����삾�Ƃق̂ڂ̂�������������̂ɁA�f��ł͋ٔ����o���o���̃X�y�N�^�N���ɂȂ��Ă���̂Ɗr�ׂ�ƁA�̂�т肵�Ă��āA�����ǂ�ł��Ȃ����ǂ̂�т芴�͌���ɋ߂��̂��ȂƎv�����B
�@���������ǂ�ł�����A��ԉf�����ŋC�ɂȂ�̂͂����ƁA�\�y�̒�����i���j�A�ɓ��荞�ނƂ��낾�낤�Ǝv���̂����A����͖����ł��邩������Ȃ��B���ƁA�����̋��낵���ɂ��ẮA�ЂƂ��Ƀe�B���_�E�X�E�B���g���̗͂Ȃ̂����ǁA�z���g�ɕ|���������B�w�R���X�^���e�B���x�ʼn������V�g���A���炵�����炢�V�g�炵���Ă��C�ɓ���Ȃ̂����A��������点�Ă������Ɩ������˂��B
�@�����]���Ƃ��ẮA������Ƃ肠�����f���ɂ����Ƃ������x�����ȂƂ����C������B���̐^���ɂ��ẮA�����ǂ�Ŕ��f���悤�B
[ �w�i���j�A������@��1��:���C�I���Ɩ����x ]
�@permalink | 
�@�����͒x����Ȃ���A�w�C�[�I���E�t���b�N�X�x���ςĂ����B������Ɗ��҂͂��ꂩ�ȁB�ƂɋA���Ă��āA�r�[���ƃ`���[�n�C������ł܂�����B���āA�^�悵�Ă������w���g���x���ςĂ݂܂����B
�@permalink | 
�@�w�C�[�I���E�t���b�N�X�x���ς��B�\����|�X�^�[�ŁA�剉�̃V�����[�[�Y�E�Z�������A180�x�J�r���ĂقƂ�Ǖ��ʏ�Ԃ̃|�[�Y���Ƃ��Ă���̂��L�������ǁA����ɏے������S�҃j���W���E�A�N�V�����̉f��Ȃ̂��ȂƎv���Ă����B
�@�ӊO�ƃA�N�V�����̘A���Ƃ������́A����������̐ݒ�̐����Ƃ��͂����āA�������A�N�V�����ɃJ�^���V�X���Ȃ��B����オ��ׂ��Ƃ���ŁA����オ��Ȃ��̂��B
�@�����ȓ���A�����Ɍ������Ă킩���Ă���̂����A�킩���������͂���Ȃɋ����ׂ����ʂł��Ȃ����B������SF�I�ݒ肪�A���������\�ȗ����o�Ă���̂͂��ƍD���Ȃ̂����A�ȗ��Ƃ������͐����s���Ɗ����Ă��܂��̂͂Ȃ�Ȃ낤�B
�@���̉f��̏ꍇ�A����ς肻���������^���́A�����܂ŃA�N�V�����V�[���̔w�i�ł����Ȃ��Ă悭�āA�h���p�`��ؗ�ȃA�N�V���������C���ł�������̂��Ǝv���B�v�l��~���āA�y���߂�A�N�V�����ł���B
�@���̒P���ȂƂ��낪�������������Ă��Ȃ���ˁB�Ƃ����킯�ŁA���\���҂͂��ꂾ�����B
�@�������O�ɁA��\�搶�̓��L�ŁA�u�w�{���f�[�W�t�@�b�V�����̏��ɓ��e����������Ƃ肠�����f��ɂȂ�x�Ƃ������ՂȔ��z�͂��낻���߂܂��B�v�Ƃ����̂�ǂ�ŏ����̂����A������v���o�����B���������ő��ʂɂ������Ă����̂́w�A���_�[���[���h�F�G�{�����[�V�����x�ŁA���ڂ́w�A���_�[���[���h�x�͋z���S�ΘT�j�̑Ό����̂ł�����ƍD���������̂Ŕ�����������ǁB
[ �w�C�[�I���E�t���b�N�X�x ]
�@permalink | 
 �@�܂��̓I�[�v�j���O����B�A�ŗ���̊G�������Ă�! ���g���������Ă�! ���Ă��������ŁA���\��������B
�@�܂��̓I�[�v�j���O����B�A�ŗ���̊G�������Ă�! ���g���������Ă�! ���Ă��������ŁA���\��������B
�@�����ǁA�I�[�v�j���O���āA�{�҂ƈ���Ĉ���Ȃ̂ŁA���\�Â����t���A�j���[�V�����Ȃ��o�Ă���̂����ʂ��Ǝv���̂����A�ӊO�ɓ��������Ȃ��B�Î~���������A�����V�[���ł����ŕ����g�ł��Ă邭�炢�ł��ƒP���ȓ����B����ł�����Ȃ�Ɍ�����̂́A�G�R���e����낤������Ȃ̂��B�ł��A�I�[�v�j���O�ł��̒��x���������Ȃ��̂��ƁA�{�҂͉����Ēm������Ȃ��Ǝv���Ă�����Ƃ�������������B
�@�{�҂̕���́A����ƑS�R�Ⴄ�B�ł��A�ׂ��ȃG�s�\�[�h������̂����炱���炩����������Ă��Ă���B�w���g���x��������Ȃ��āA�w�f�B�X�R�~���j�P�[�V�����@����ҁx�Ȃ̃G�s�\�[�h�������āA���͋C�I�ɂ́u���g���v���[���h���Č����Ă���Ƃ�����ہB
�@�Ō�̃N���C�}�b�N�X�ŁA�u�V�ԁv�Ƃ��ɂ͕ό`���{�Ƃ��g���ė~�����Ƃ��v�������ǁA�܂��������B
�@��1�b�̓W�J���炷��ƁA1�b�����ōŌ�ɖ��g���������u�V�ԁv�Ƃ����X�g�[���[�ł����̂��낤���B��������̂܂܂͂���ς肫���̂ŁA���������̂�������������Ȃ��B�u���g���v�O�`���Ă����������ȁB
�@�Ƃ������ƂŁA������ς�\��B
[ �w���g���x ��1�b�u���n�߁A�J�̋����v ]
�@permalink | 
�@�������f����ςɍs���B�����A�ς��̂̓W���b�L�[�E�`�F���剉���wTHE MYTH�^�_�b�x�B�����̃W���b�L�[�E�`�F���f��Ƃ͂�����ƈႤ�B�wHERO�x�wLOVERS�x�݂����ȗ��j���̂ƌ����ɂ��������W���b�L�[�E�`�F���f�悪�Z�����Ă���Ƃ����Â������́B�q���C���̃L���E�q�\�����Y�킾�����B
�@permalink | 
�@�wTHE MYTH�^�_�b�x���ς�B�����̃W���b�L�[�E�`�F���̉f��Ƃ͂�����ƈႤ�B�`�̎���ƌ���Ƃ̘b�����݂ɑ����A�Ō�ɂ��ꂪ��Ɍq�����āA���C���[�A�N�V��������̃N���C�}�b�N�X�B�W���b�L�[�E�`�F���́A����ł͍l�Êw�ҁA�`�̎���ł͏��R�Ƃ����A��l����������Ă���̂����A����͕��i�̃R�~�J���ȃW���b�L�[�E�`�F�������A�`�̎���̓j�R���Ƃ������ɐ^�ʖڂȊ�Œʂ����A�J���t�[�ł͂Ȃ����⑄�Ő키�Ƃ����S���Ⴄ���͋C���B
�@�`�̎���̃G�s�\�[�h�́A�wHERO�x��wLOVERS�x�ɑR���Ă���ȂƎv���B�����A������ςĂ��āA���j���̂悤�Ȃ��̂����ꂾ���͂���Ă��A�W���b�L�[�E�`�F��������܂ł��������f��ɏo�Ȃ��������R���Ȃ�ƂȂ��킩�����B���^�ʖڂȊ�������W���b�L�[�E�`�F���̎�����Ȃ����ƁB�܂��A���R�Ƃ������Ƃł��Ԃ��Ă���h��������Ȃ��B�ǂ������Ă��A�W���b�L�[�E�`�F���ɂ́wHERO�x��wLOVERS�x�͖����������B
�@����Ȃ킯�ŁA�`������`�̎���̃G�s�\�[�h�Ŏn�܂�ƁA����œԂ͐h���Ȃ��Ǝv���Ă��܂����B�Ƃ��낪�A�R���痎�����W���b�L�[�E�`�F���͌���Ŗڂ��o�܂��A�܂��������������Ƃ����B��������n�܂錻��̘b�͋t�ɃR�~�J���ŃW���b�L�[�E�`�F���͂������̕��������Ɛ����������Ă��Ă����B���������܂�ɓ�̕���ɃM���b�v�����肷���āA����ς肱��͎��s�Ȃ�Ȃ����Ǝv�����̂����A�N���C�}�b�N�X�̉ߋ��ƌ��オ���т����ɂ͌��\�ʔ����Ȃ��Ă����B���㕔���ł́A���d�͂��N����覐̓�Ȃǂ��łĂ���̂����A���ꂪ�ǂ��ߋ��̘b�Ɍq����̂��Ǝv������A�g���f���Ȋw�I�Ȍ������N���C�}�b�N�X�̕�������o���d�|���ɂȂ��Ă�̂��悩�����B
�@�����I�ɂ́A�S�җ��j���݂����Ȃ��͍̂���Ȃ��W���b�L�[�E�`�F�����A����̘b�ƍ��킹�Ă܂Ƃ߂������̂͂悩�����̂��ȂƎv���B����ƃq���C���̃L���E�q�\���������ꒃ�Y�킾�����B�`�̎���ɃW���b�L�[�E�`�F�������鏫�R�Ƃ̗��͂��Ȃ�Ȃ��������A�N���C�}�b�N�X�Ō���̃W���b�L�[�E�`�F���Əo��B�����܂ł�����A���ʃn�b�s�[�G���h�ɂ������Ȃ����A�ߗ��ŏI��点�Ă��܂��̂́A����ς���j�����̂��ӎ����Ă���̂��ȁB�ǂ����^�ʖڂԂ�����̃W���b�L�[�E�`�F���͎�����Ȃ�����A�Ō�͂��o�J�ȃn�b�s�[�G���h�ɂ��Ă��܂������Ă悩������Ȃ����Ǝv���̂����B
[ �wTHE MYTH�^�_�b�x�@�݂䂫�� ]
�@permalink | 
�@�w�g�����F���[�x�i�W�����E�g�E�F�����E�z�[�N�X�@�\�j�[�E�}�K�W���Y�j�Ǘ��B��҂��Ƃ����ɂ��ƁA�O����炵���i������m���ł͂Ȃ��炵�����j�B�ꉞ�̊����͂��Ă���̂����A���҂���������A�������悢�敨��̎n�܂肾�Ƃ��������B�w���[�h�E�I�u�E�U�E�����O�x�̈��ڂ��ϏI��������̂悤�ȁA�����ŏI������Ⴄ�̂���Ƃ��������B�ł��A����������ǂ݂����Ƃ��������͂Ȃ��āA�ʂɂ��̂܂܂ł��������ȂƎv���Ă��܂����B�\����Ȃ��B
�@�w�E�l������ �q�ؒf���ꂽ���̖̂��r�x�i���ҍs�l�@�u�k�Е��Ɂj���ēǂ���B
�@�挎�A�w�����E�l�����@�E�l�������U�x�i���ҍs�l�@�u�k�Е��Ɂj���u�k�Е��ɂɓ����āA�^�C�g���́w�����E�l�����x���Ȃ�ƂȂ������Ȃ��Ǝv�����̂����A�悭������T�u�^�C�g���Ɂu�E�l�������U�v�Ƃ���킯���B����Łw�E�l�������x���Ăǂ�Șb���������ȂƎv���Ďv���o�����Ƃ����̂����S���v���o���Ȃ��B�{�I����T���āA�p���p���y�[�W���J���Ă��킩��Ȃ��B�ӂ��A�b��Y��Ă��Ă��p���p���߂��邾���ő�̎v���o���̂����A�S���v���o���Ȃ��B����œ��ڂ�ǂޑO�ɂ�����x���ڂ�ǂݕԂ����Ǝv�����̂ł���B
�@���y�[�W�ǂ�ł��S�R�L���ɂȂ��̂ŁA���������Ĕ������܂ܓǂ�ł��Ȃ��̂��Ƃ��v�������A���炭�ǂ�ł����炾�ڂ낰�ȋL�����S��B�Ƃ͂����A�Ɛl���g���b�N���S���o���Ă��Ȃ��B
�@���Ȃ݂ɁA�w�����E�l�����@�E�l�������U�x��10�N�ȏ�O�̍�i�B
�@permalink | 
�@�u�A���t�F�A�v�ɗ\�z�O�ɂ͂܂��Ă��܂����̂ŁA�t�X�^�[�g�̃h���}���������Ă݂悤���Ǝv���āA�u�N���T�M�v�����Ă݂��B����͓��^�C�g���̃R�~�b�N�w�N���T�M�x�B�ŋ߁A�R�~�b�N�X������̃h���}�Ƃ��f�摽���Ȃ��B���ڂ̊��z�́A�܂�Ȃ��͂Ȃ�����ǁA�u�A���t�F�A�v�Ȃ݂ɂ͂܂肻���ł͂Ȃ������B����Ƃ̈Ⴂ���C�ɂȂ�B
�@permalink | 
 �@�w�_�E���B���`�E�R�[�h�x�̕ҏW�҃W�F�C�\���E�J�E�t�}�������o���������̍�Ƃ̐V�V���[�Y���Ƃ����B���̑т̎��ɂ��A�u�w�_�E���B���`�E�R�[�h�x�̃`�[�����͂ȂŐV�����v�Ƃ��ŁA�ҏW�҂��ǂꂾ�������ɉe���x�������Ă���̂��^�₾���A���̕ҏW�҂̃^�C�v���ƂƂ̃R�~���j�P�[�V�����̎����̈Ⴂ�ɂ��̂ŁA���ۂ̂Ƃ���͂Ȃ�Ƃ������Ȃ��B�����A�u�`�[���v�Ƃ����̂͂ǂ��Ȃ낤�Ƌ^��Ɏv�����A�E�F�u�T�C�g�𗧂��グ�đ�X�I�ȃL�����y�[�������āA�f�扻�����܂��Ă���Ƃ������ƁA�܂��Ƀ`�[���ɂ��d���Ȃ̂�������Ȃ����B
�@�w�_�E���B���`�E�R�[�h�x�̕ҏW�҃W�F�C�\���E�J�E�t�}�������o���������̍�Ƃ̐V�V���[�Y���Ƃ����B���̑т̎��ɂ��A�u�w�_�E���B���`�E�R�[�h�x�̃`�[�����͂ȂŐV�����v�Ƃ��ŁA�ҏW�҂��ǂꂾ�������ɉe���x�������Ă���̂��^�₾���A���̕ҏW�҂̃^�C�v���ƂƂ̃R�~���j�P�[�V�����̎����̈Ⴂ�ɂ��̂ŁA���ۂ̂Ƃ���͂Ȃ�Ƃ������Ȃ��B�����A�u�`�[���v�Ƃ����̂͂ǂ��Ȃ낤�Ƌ^��Ɏv�����A�E�F�u�T�C�g�𗧂��グ�đ�X�I�ȃL�����y�[�������āA�f�扻�����܂��Ă���Ƃ������ƁA�܂��Ƀ`�[���ɂ��d���Ȃ̂�������Ȃ����B
�@�����Ȃ�Ə����Ƃ������́A��������f��A�ʂĂ̓Q�[����A�~���[�Y�����g�p�[�N�ł̃A�g���N�V�����܂Ŋ܂߂������G���^�e�B�����g�̃v���W�F�N�g�Ȃ낤�B�����瑍���G���^�e�B�����g�ɔ����������͂Ȃ����A���������b���Ă��܂��Ə����Ƃ��ēǂދC�͂͂��Ȃ茸�ނ���B�Ƃ��낪�A���̑�X�I�Ȑ�`�ɑ��āA��҂́u�n��̃p���[���E�����v�Ƃ������R����\�ɏo�Ă��Ȃ��Ƃ����̂ł�����Ƌ������������B�v���t�B�[���ɂ́A�u�O���b�h���痣��ĕ�炵�Ă���v�Ƃ�����s�݂̂��Ƃ����B
�@�O���b�h�Ƃ́A�����̒��ɂ��łĂ��邪�A����̕��������鎋�_���璭�߂��Ƃ��A�c�����Ƃ�{�v���O�����́A�H���Ă����ΒN�̋��ꏊ�ł��˂��~�߂���O���b�h�|�|���Ȃ킿�i�q��̏��ڂɂȂ��Ă���Ƃ����B����Љ�ɐ�����Ƃ��̃O���b�h���瓦��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�O���b�h�ɂЂ������邱�ƂȂ�������ɂ́A�n���o�ςɊւ��d�������邩�A���₭�ړ����邵���Ȃ��B
�@����Ȃ킯�ŋ����������ēǂݎn�߂��B����̓g�����F���[�Ƃ����ʂ̐��E�ɍ��̂悤�Ȃ��̂��ړ��ł���͂����l�X�ƁA�g�����F���[���E�����Ƃ���^�r�����Ƃ����g�D�A�����ăg�����F���[����邱�Ƃ��g���Ƃ��Ă����n�[���N�B���Ƃ����ꑰ�̐킢�̕��ꂾ�B�g�����F���[�����҂ŁA�^�r�����̖ړI���Ȃ�Ȃ̂����X�͕���̒��ŏ��X�ɖ��炩�ɂȂ��Ă������A���ǁw�g�����F���[�x�����ǂݏI���Ă��܂����ׂĂ͂킩��Ȃ��B
�@�Ƃ������A�����܂ł����҂���������A�{���̕���͂��ꂩ��n�܂�Ƃ����������ɉ߂��Ȃ��B�S�̂��ǂꂾ���Ȃ̂��s�������A����Ɋ��ΎO����̑���炵���B�l�Z��600�y�[�W��̖{�ŁA�܂��O���̈�Ȃ���{�����[���͂��邪�A�ǂ������҂��Ă����قǂł͂Ȃ���Ȃ��B
�@�ݒ�I�ɂ͓`����I�ȗv�f������SF�I�Ȃ̂����ASF�I�Ȃ̂͐ݒ�ŏI����Ă��܂��āA���ꎩ�̂͂����܂Ŗ`�����̂ł����Ȃ��B�`�����̂ł������킯�ł͂Ȃ��̂����A�܊p��SF�I�Ȑݒ肪��������Ă��Ȃ��C�����Ă��܂��̂��B�����A�܂����҂�������������Ə���������ǁA�b���s��Ȃ̂ł͂Ȃ��āA�������Ɉ�̎R����}���Ă���̂ɁA���������������Ȃ������Ȃ̂�������Ȃ��B
�@�������A�f��Ȃ�T�X�y���X����̃A�N�V�������̂ɂȂ�Ǝv���B�ł��A������Ɛh���̊��z��������Ȃ����ǁA�����Ƃ��Ă͂ނ���O���b�h�̕|���Ƃ��A�g�����F���[�ƃn�[���N�B���ƃ^�r�����̌��̓`��I�ȗ��j�������Ɠǂ܂��Ăق����Ǝv���Ă��܂��̂��B
[ �w�g�����F���[�x �W�����E�g�E�F�����E�z�[�N�X�@�\�j�[�E�}�K�W���Y ]
�@permalink | 
 �@�N���T�M������B
�@�N���T�M������B
�@����̓R�~�b�N�X���w�N���T�M�x�Bamazon�̏Љ���Ɏ��̂悤�ɏ�����Ă���B�u���ɎO��̍��\�t����B���l���x���A���K�������グ��g�V���T�M�h�B�ِ����a�Ƃ��A�S�Ƒ̂�M�ԁg�A�J�T�M�h�B�����Đl�����킸�A�V���T�M�ƃA�J�T�M�݂̂���炤�g�N���T�M�h������B�Ƒ������֒ǂ�������V���T�M�����A�����V���T�M�̂�炤���ƂU�̖ړI�Ƃ���j�́A���Q�̕��ꂪ�n�܂���!�v�B
�@����͓ǂ�ł��Ȃ��̂����A����܂�amazon�̓��e�Љ�炷��ƁA����̑�1�b�A��2�b�́u���c�Z�����\�v���h���}�̑�1�b�̌��ɂȂ��Ă���悤���B�h���}��2�b�̂��炷�����T�C�g�ɏo�Ă��邪�A��������낢��r�F���Ă��銴���B��1�b�͔�r�I����ɋ߂��̂�������Ȃ����A�ǂ��Ȃ낤�B
�@�h���}��1�b�́u���c�Z�����\�v�ŁA���ɂ��Ď�����������������̂����āA�w�����̎��p�x���v���o���B�w�����̎��p�x���V�˓I�Ȓm�\�Ƃ̘b�Ɋr�ׂāA������̃V���T�M�͂������Ȃ��N���T�M�ɛƂ߂���B���\�̎������̌����ꂾ�Ǝv���̂����A�h���}�ŕ`����Ă��邾�����Ƃ���ȊȒP�ɍ��\�t���x�����̂��Ǝv���B
�@��x�̓N���T�M�̎���Ɏg�����Ђɋ^��������Ȃ���A�ȒP�ɗH���Ђ��������肵����Ђ��ƐM���Ă��܂��Ƃ���Ƃ��A���؎�𗘗p�����e�N�j�b�N�Ƃ��V���T�M���g���悭�m���Ă��邱�Ƃł͂Ȃ��̂��Ƃ����^��B���\�t�䂦�ɁA�x���Ă��鎩�����x����Ă���Ƃ͋C�Â��Ȃ��Ƃ����̂͂���Ǝv�����A�����͂�������B
�@�h���}�̃��A���e�B�́A���ׂĂ����ׂă��A���ł���K�v�͂Ȃ����A���߂Č��Ă���u�Ԃɂ͂Ȃ�قǂƎv�킹�Ȃ��Ă̓_�����Ǝv���̂��B���\�̎�������̃h���}�̈�Ԃ̊̂��Ǝv���̂ŁA���̕����Ńh���}�̉R�Ƃ����̂�������Ă��A���\�̎���ʼnR���ۂ��������Ă��܂��Ƃ��Ȃ�h���B
�@����ł͂��̕ӂ̂Ƃ���͂ǂ���������Ă���̂��A����������B
[ �N���T�M ]
�@permalink | 
�@���x���������ɑ����ڂ��o�߂�B7���߂��ɋN���āA���L����������AWeb���A�N�Z�X������B���̂����Ȃ�ƂȂ������Ȃ��Ă����̂ŁA�ĂѐQ��B���x�͒����ڂ��o�܂��B
�@�����͂�����x���̒��̎��ԑтɍ��킹�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����A�x���͖{�\�̕����܂܂ɖ����Ȃ�ΐQ��A�ڂ��o�߂���N����Ƃ����̂��ŋ߂̎�`�ł���B���ƁA�Ђ����疰�葱���Ă݂����A24���ԂƂ������ƒ�������ȏ㖰��Ȃ��Ƃ����܂Ŗ����Ă݂������A���Ԃ�Ȃɖ���Ȃ����낤�B���ƁA�[���ɂ��Ȃ肻���ȋC������B
�@���Ԃ͍������w�E�l������ �q�ؒf���ꂽ���̖̂��r�x�i���ҍs�l�@�u�k�Е��Ɂj��ǂށB�Ƃ肠�����A�������炢�܂œǂ��A�����Ԏv���o���Ă����B�������A�o��l���̃L�����Ȃ͑S���L���Ɏc���ĂȂ��B�ǂ��������Ƃ��ȁA�S���B
�@permalink | 
|
|
|
|
 |